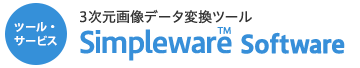事例インタビュー:香川大学 自然生命科学系(医学部) 形成外科学講座
形成外科でのCAE活用と今後の展望
先入観をなくせば、医工連携は極めて自然
香川大学の形成外科では、手術をする前に患者さんのCTデータから再構築した3次元モデルを使って、あらかじめ模擬手術をされています。医工連携を進める上でのご経験や今後についてお聞きました。

国立香川大学 自然生命科学系(医学部) 形成外科学講座 主任教授 永竿 智久 先生
Q01 医師としてシミュレーションを始められたのはいつごろからでしょうか。
 誰がやっても良くなる手術方法を開発しなければ
誰がやっても良くなる手術方法を開発しなければ
ならない
永竿先生 : アイデアを持ったのは1997か1998年ぐらいです。かれこれ19年ぐらい前になります。構造解析と有限要素法を勉強して、ベーシックなものですが、自分でプログラムを組んだことがあります。しかし、そのプログラムでは自分が研究したいことが出来ないと分かり、商業のソフトウェアを使い始め、専門的にやるようになったのは大体、2000年ぐらいですかね。
Q02 きっかけは何だったのでしょうか。
永竿先生 : 形成外科の仕事では、骨とか皮膚とか、筋肉など、体の器官を伸ばしたり、形を変えたりすることが非常に多く、力というのが少なからず問題になってくるというのを現場の中で気づき、それがきっかけで始めました。
Q03 どのように工学分野を学ばれたのでしょうか。

永竿先生 : 臨床医になって10年弱だった頃、最初は有限要素法について勉強し、構造解析の知識を学びました。私はもともと数学が好きだったので、仕組みを理解してから実際のソフトウェアをいじるようにしていきました。
医学から工学というと、かなり飛躍というか全く別の分野と思われているきらいがあるのですが、そういった分野に関する先入観がないと、医学でも極めて工学的な発想をします。例えばこれ、ご覧になって分かりませんか。
頬骨骨折例でここのところが折れて、こちらは明らか落ちてしまっていますよね。だから、この骨を元の位置に戻して止めなければなりません。止めるには、ミニプレートという、小さなネジを使うのですが、建築を行う際でも、適当にくぎを打ったらそこの柱が崩れたりしますよね。
 頬骨骨折固定応力解析
頬骨骨折固定応力解析
それと同じことが骨でも起こります。例えば骨を戻してここにプレートで止めるとします。ところがこの骨も黙ってここにいられるわけではなく、周りに筋肉でついていますし、皮膚によって圧力も受けます。だからせっかく止めてもネジが外れたり、ネジとともに固定した小さなプレートが少し曲がってしまうことはよくあります。これを「技術者の経験」とか「きちんと手術をすればそうはならない」という方もいるのですが、私は誰がやっても良くなる手術方法を開発しなければならないと思っています。
頭蓋骨の部分をネジとプレートで止めるときは、建築でドアを作るときの蝶番と同じような感じで、このような論議は医学の学会でもよくされています。しかし、それに関する客観的なエビデンスを与えようという試みは出ていませんでした。ご年配の先生が経験から「これはこうじゃなきゃ駄目」とか「ネジは太いものを使わないといけない」と言っても、僕はかなりそれに反発を感じていました。
同じネジを使うにしても、直径が2ミリのネジと4ミリのネジだと、患者さんにとっての負担が全然違います。
直径が太いネジを打つと、あとで気になりますし、そのネジを使うためには1センチで済む傷を3センチにしなければなかったりします。
手術で骨の位置を元に戻して、固定するのは、まさに大工さんと同じ発想なので、医学とか工学とか、そういう先入観をなくして考えた場合には極めて自然なことなのです。医学からよく工学にジャンプをしますねと、よく言われるのですが、考えてみると当たり前のことなのです。手術を勘に頼っている人たちもいますが、テクノロジーが発展している現代では、人体は住宅やマンション以上に、より緻密に計画が練られてしかるべきではないでしょうか。顔の骨を整復する上でも効率的に少ない固定部位で固定するってことは必要なのです。

私の専門分野で漏斗胸という病気があります。漏斗胸の本質はあばらの変形です。凹んでいる肋骨を治すのですが、患者のCT画像から3Dモデルを作成し3Dプリンティングする場合も骨と軟骨の部分の素材を分けて作成します。
何番目の骨を外せば、うまく骨全体が上がってくるのかを手術の前に検討し、決めなければいけません。だから形を変えるという点では、医師が行っていることと大工さんが建築で行っていることは、ほとんど同じなので、建築でCADが使えるのと全く同じような意味で医療でもCAEが有用だということです。
また唇裂という病気も割と多く500人に1人くらい発症しているのですが、これもどうやって治すかっていうと、手術でもちろん治すんですが、手術方法に関して昔から発展してきて、いろんな方法があるんです。単純に考えると縫えばいいように思うかもしれないけれど、無理やり縫っても傷が開いたりするんです。だからどういうふうにデザインして皮膚を縫うかっていうことが昔から研究されてるんです。
Q04 形成外科の分野で、CAEは今後どのように有効活用できそうでしょうか。
永竿先生 : 手術をする前に患者さんのCTデータから再構築した3次元のモデルを使って、あらかじめ模擬手術をしています。人間の体は、骨を1センチメートルずらすだけでも結構血が出てしまいます。何気なく手術を始めてしまうと、それで手術の時間も長くなってしまうので、手術の前にどういう手術をやるかを緻密に考えておかないとなりません。手術はあらかじめ考えたプランに沿っておこなっています。プラモデルだったら切り離して単純に接着剤でくっつければそれで話は済みますが、実際は目もありますし、皮膚もあります。現実の手術は難しく、こことここだけで、これをうまく止めなければならない、あるいはここは危険だから避けなければならないということも必要になってきます。家を作る際にもありますよね。そういうところはシミュレーションで確認すべきだと思います。
Q05 将来JSOLにご希望されることはありますか。

永竿先生 : 皆さんはよくご存知かもしれませんが、軟骨を三次元的に描出するというのは、すごく大変です。今は手作業で行っています。CTなりMRIで、骨は割と自動的に抽出できるため、骨のモデルを作るのはあまり苦労しません。ところが手術をすると、骨以外のものが問題になってくるってことは非常に多く、その代表的な例が軟骨です。今は、画像のスライスを1枚1枚トレースしながら手作業でやっています。
具体的になりますが、軟骨の部分を抽出するようなプログラムを開発して欲しいです。今は、CTやMRIの閾値だけで選択していますが、やっぱり無理ですね。パターン認識のようなプログラムを取り入れられるんじゃないかと思うんです。
少し、別の話になりますが、手足が動かない人が目の動きだけでコンピュータのキーボードを操作する研究をしたことがあります。機能させるためには、目玉の動きをディテクトする必要があります。人間の目には、黒目と白目がそれぞれありますよね?そういう色合いで急速な勾配が1センチか2センチの間にあるものは目玉以外の構造であんまりないです。黒と白でなおかつ動くものといったら、この部屋の中を見ても目玉ぐらいしかありません。だから瞬時に認識できるのです。軟骨についても同じで、単純に閾値だけを抽出するのは、軟骨が認識できないと思います。近くに骨があった場合、軟骨の勾配があって閾値の勾配があって、というものから自動的に、軟骨を認識するようなプログラムがあればそのモデルを作る基となるSTLデータが簡単にできると思います。
さらにこれを膨らませれば、ある患者さんのデータがあったら自動的に有限要素モデルとして抽出して、それをメッシュ生成できるようなことが可能になってくるのではないかと思うんです。
 漏斗胸応力解析
漏斗胸応力解析
JSOL : 同じ要望は結構ありまして、軟骨のようなものはCTには写らず、MRIでも結構抽出するのは大変なので、自動認識やデータベースで集めたものをAIで対応できないかという取り組みも議論されています。すぐにとはいかないと思いますが、そういったニーズはとても多いため、簡単にできるときが来ると思っています。軟骨とかじん帯のように本当にちょっとした微小な色の違いというのを、エンジニアは分離できないので、医師の経験や認識をプログラムに入れられたら、いいですね。
永竿先生 :
シミュレーションっていうと未来のものというか、夢の世界というかファンタジー、SFみたいなところが今まではあったかと思うのですが、今はかなり正確に物事が把握できるようになっているわけだし、予測という言葉のほうが良いかもしれませんね。あるいはプレディクションっていう言葉の方が良いと私は思っています。それぐらい身近なものになっていくでしょう。
医学の世界にも、流行廃りがあって、過去は最新医学が15年くらいずっと盛んで、工学分野をやってきた人はあまり多くありませんでしたが、今後ますます脚光を浴びてくるかもしれませんね。実際に大変有用な取り組みですから医学の中で、こういった研究を行う人口が増えてくるのではないでしょうか。
-
国立香川大学 自然生命科学系(医学部) 形成外科学講座 主任教授
永竿 智久 先生
- 【ご略歴】
-
- 私立 開成中学校・高等学校卒
- 1990年 慶応義塾大学医学部卒
- 1990年 慶応義塾大学病院形成外科研修医
- 1991年 富士重工総合太田病院外科医員
- 1994年 静岡赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道科医員
- 1995年 国立弘前大学形成外科文部教官助手
- 1996年 慶応義塾大学形成外科専修医
- 2002年 慶応義塾大学病院形成外科助手
- 2005年 慶応義塾大学医学部講師
- 2011年 慶応義塾大学医学部専任講師
- 2012年 慶応義塾大学医学部准教授
- 2014年 国立香川大学医学部准教授
- 2017年 国立香川大学医学部主任教授
- 事例インタビュー協力
-
香川大学
自然生命科学系(医学部) 形成外科学講座
所在地:〒761-0793
香川県木田郡三木町池戸1750-1
連絡先:087-898-5111
公式サイト:http://www.kagawa-u.ac.jp/ -

活用事例一覧
- 工業分野
-
- オープンソースライブラリで画像分析 - 多孔質体画像分析ライブラリPoreSpyとSimpleware Softwareの連携事例
- 金属積層造形部品の微細構造の特徴を捉える
- 現物のボイド(空隙)を考慮した繊維複合材の破断解析
- 3Dプリンティング技術により積層造形されたアルミ合金ラティス構造の品質保証の考察
- 非経口バイアル瓶の完全性を目的としたX線CTによるストッパーの封止工程の可視化
- Simpleware Softwareによる天然植物繊維の形態観察 - 繊維モデル
- Agナノ粒子焼結体の低温クリープ挙動
- Simpleware SoftwareとJMAGの連携による磁界解析 - トロイダルコイル
- 医工連携
-
- 流体構造連成解析を用いた嚢状腹部大動脈瘤に対するステント留置の力学的評価
- マイクロCTによる3D積層造形品の幾何的精度の考察
- 血管内デバイス開発におけるSimpleware Softwareの活用
- 不完全に並置された冠動脈ステントにおける血栓形成の医療画像分析
- Simpleware SoftwareとLS-DYNAの連携による生体解析 - 胸腰椎
- Simpleware SoftwareとLS-DYNAの連携による強度解析 - 腕神経叢モデル
- Simpleware SoftwareとLS-DYNAの連携による強度解析 - 人工膝関節モデル
- Simpleware SoftwareとCAEの連携による応力解析 - 大腿骨モデル
- Simpleware SoftwareとLS-DYNAの連携による強度解析 - 人体鎖骨モデル
- ※株式会社JSOLはSimpleware Softwareの正規代理店です。
- ※Simpleware Software の開発元は、Synopsys, Inc.(米国)です。
- ※記載されている製品およびサービスの名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。