
CAE Technical Library CAEブログ - CAE技術情報ライブラリ
2008.08.01
6月9、10日の2日間、米国デトロイトにおいて通算10回目となるLS-DYNA国際会議が開催されました。米国での国際会議は1年おきに開催されています。会場は今回もデトロイト郊外にあるホテルHyatt Regency Dearbornで行なわれ、基調講演、一般講演を合わせ100件近くの技術発表がありました。今回の国際会議でとくに注目されたトピックスや会議の様子についてリポートします。

1.国際会議の構成
1日目の午前と2日目の午後は基調講演を中心とした全体セッションがもたれ、その他の時間は5室に分かれてパラレルセッションが進められました。各セッションの発表件数は図2のようになっています。従来から自動車の衝突安全に関する事例発表が多いのですが、今回はそれにも増して比較的最近LS-DYNAに実装された機能や開発中の陰解法用機能を用いたメタルフォーミングの事例が目につきました。
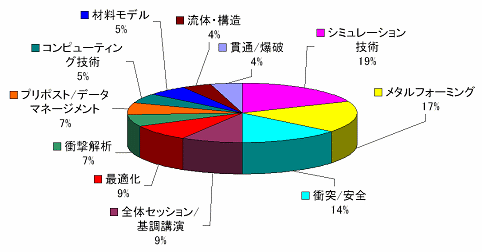
2.基調講演
今回の国際会議で基調講演を発表された方々と講演タイトルは次のとおりです。
聴講した講演については概要も付け加えています。
●Mr. Tsuyoshi Yasuki (Toyota Motor Corporation), Lessons Learned from Crash Analysis by the Earth Simulator
今後大規模クラスターを用いて設計開発に用いられることが予想される1,000万を超える要素数からなる車両衝突モデルを地球シミュレータを使用して実行して得られた知見と将来展望について。
● Mr. Nand K. Kochhar (Ford Motor Company), Advancements of Safety CAE within Ford
フォード社における現在のCAEの取り組みと将来計画について。CAEを設計ツールとして活用するため、応答曲面法だけでなくGAも含めた最適化の適用、モーフィング技術の応用、現在の課題としてロールオーバー、下肢傷害等、将来的な計画としてCFDとのカップリング、衝突モデルの陰解法による初期化などを挙げていました。
● Dr. Ted Belytschko (Northwestern University), Developments in Computational Science and Engineering
マルチスケール解析やマルチフィジックス問題など、最近計算力学でトレンドとなっている話題を取り上げ、様々なアプローチを紹介していました。またNURBS曲面を用いたFEM解析など最先端の研究についても言及されました。
● Dr. Chuan-Tao Wang (General Motors Corporation), Autobody Manufacturing CAE - The Business Needs and Technical Challenges
● Dr. Rahul Gupta (U.S. Army Research laboratory), Multi-Phase, Multi-Material, ALE Approach for Buried Blast Simulation
Mr. Paul Du Bois (Consulting Engineer), Simulation of Polymeric Materials in LS-DYNA
プラスチックのモデル化がホットなテーマとなっていますが、ほとんどのプラスチックの挙動は従来からあるLS-DYNAの多直線近似弾塑性体モデル *MAT_024(*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY)をうまく適用するとモデル化可能であるという実例が示されました。さらに *MAT_024 ではどうしても表現できない"クレージング"現象をモデル化するため、新しく開発された材料モデルの概要についても説明されました。
● Dr. John O. Hallquist (LSTC), LS-DYNA Development
LSTC社の開発コンセプト、ダミーモデル、バリアモデルの開発計画、LS-DYNA Version 971 Release 3, Release 4 および Version 980 に実装された、または実装予定の新機能(電磁気解析、非圧縮流体ソルバー、圧縮性流体ソルバー、暗号化入力データ、陰解法MPP、粒子法(図3)、メッシュフリー、陰解法と陽解法のよりスムーズなスイッチングなど)が発表されました。
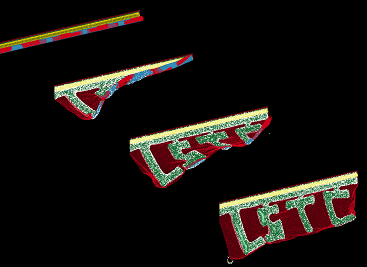
3.テーマ別セッションの概要
衝突/安全
ダミーモデルのサプライヤーからはES2、WorldSIDなどのダミーモデル開発の現状の報告、自動車メーカーからは各種ダミーモデルによる傷害値の比較などの発表がありました。そのほか粒子法を用いた実機レベルのエアバッグモデルの展開シミュレーションに関する発表もありました。
メタルフォーミング
LS-DYNAの陰解法機能の中で塑性加工シミュレーション向けに開発が進んでいる機能のいくつかがLSTC社より紹介されました。すなわち自重たわみを考慮したシミュレーションのための *CONTROL_IMPLICIT_TERMINATION、陽解法では動的な効果のため妥当な解が得られにくいフランジ曲げなどに適用されることを想定した、陰解法用の新しいコンタクトロジック「モルタルコンタクト」などです。さらに世界的に著名な研究者であり、LS-DYNAの主要な開発メンバーのひとりでもある University of California, San Diego の Dr. Benson からはNURBSベースのサーフェースを通常のFEM要素の代わりに用いるFEM解析のトライアル事例の発表がありました。この方法の有効性が実証されれば、有限要素で離散化する誤差がなくなり、画期的な新手法となることが期待されます。
シミュレーション技術
ユーザー事例として岩石崩落による被害を低減するための道路シェルター、車両用障壁などに用いられるコンクリート材料を用いた衝撃解析、溶接による残留応力の評価、軸方向・曲げ複合荷重が負荷された大腿骨の強度解析、航空機の落下衝撃、バードストライクなどLS-DYNAの豊富な機能を使用した様々な分野の応用例が発表されました。
最適化
LS-DYNAに付属する最適化ソフトLS-OPTの応用例を中心として、LS-OPTの感度解析結果を直感的に表示するツールの紹介、クラスターを用いた最適化計算のターンアラウンドタイムの短縮などが発表されました。LSTC社からはLS-OPTに新たに実装された最適化手法Radial Basis Function Networks(RBF)を衝突解析に応用し、貫入量と変位-荷重カーブを最適化した事例紹介がありました。RBFと従来のNeural Network(NN)との比較により、RBFを用いることでより少ないサンプリング数で効率的に最適解が得られることが示されていました。
プリポスト/データマネージメント
LS-DYNA用プリポストプロセッサーPRIMER, D3PLOTがJavaScriptインタープリターが内蔵され、これによって入力データ作成、後処理などのタスクの自動化が可能となりました。当日はデモンストレーションが行なわれました。また、実物のスキャンデータから有限要素モデルを生成するツールの紹介もありました。
コンピューティング技術
ハードベンダーによるHPCクラスターのアーキテクチャー、ベンチマークテストの報告などが行なわれました。またLS-DYNAのパフォーマンスを最適化するためのネットワークシステム構築の提案もありました。
材料モデル
スペースシャトルの強化炭素複合材(Reinforced Carbon-Carbon)を積層シェル要素でモデル化した事例(これはLS-DYNAのひずみ速度依存複合材料モデル *MAT_RATE_SENSITIVE_COMPOSITE_FABRIC の使用例になっています)、周期荷重による疲労・破壊をモデル化するためにLS-DYNA最新版に実装された *MAT_DAMAGE_3(移動硬化と等方硬化を組み合わせたダメージモデル)を用いたブレースフレームの破断のシミュレーション、プラスチックの"クレージング"をモデル化するため塑性ポアソン比を導入したプラスチックモデル *MAT_SAMP-1 を用いたシミュレーションと実験との比較、複合材チューブの圧壊など複雑な材料挙動をモデル化するための様々な材料モデルが紹介されました。
流体・構造
複合材料で構成された衝撃緩衝装置を取り付けた航空機、ヘリコプター等が水上に胴体落下した実験結果(加速度)をALE、SPHを使用したモデルで再現したNASAの発表がありました。ALE、SPHとも離散化の精度が充分であれば実験結果を再現できることが示されました。LSTC社からは新機能として実装予定の流体解析機能、すなわち非圧縮流体CFDソルバー、2D to 3D ALE Mapping、Conservation Element and Solution Element (CESE)法を用いた新しい圧縮性流体ソルバーのプレゼンテーションがありました。いずれもリリース時期は未定ですが、LSTC社としては圧縮/非圧縮流体ソルバーとも構造との相互作用を考慮した開発を進めています。
貫通/爆破
積層材(CFRP)、樹脂-木材のサンドイッチ構造物、炭素/ガラス繊維複合材などの貫通シミュレーション、強度解析、SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)法を用いたバードストライク解析事例などの発表がありました。多様な材料のモデル化事例として参考になる発表が多くみられました。
●まとめ
車両衝突解析の関係ではハニカム、スポット溶接破断などいくつかの技術課題が残るものの、一定の成果を得ながらより正確に、より速く、を追求しており、今後乗員傷害値のより正確な予測へ進んでいくと思われます。その中で現状のダミーモデルに対する精度不足がいくつか言及されており、今後ダミーモデルの詳細化/高精度化が加速すると感じられました。
材料モデルでは、特にプラスチックと複合材(CCFRPなど)への関心が高いようにみうけられました。流体構造相互作用(FSI)は従来のALEを用いて実績をあげるというよりも、非圧縮流体や粒子法など、他の新しい手法を試行しているというR&D的な発表が多くありました。特に開発中の粒子法(*AIRBAG_PARTICLE)に関する講演が2件あり、注目を集めていました。MPPでのスケーラビィティの改善や粒子の可視化などについて講演者からLSTCに要望が挙がっていました。
LS-OPTを用いた最適化の報告も多くありました。テーマとしては実用的な観点から応答曲面法を用いた最適化、もしくはロバスト設計の二つに集約されていました。LSTC社長ホルキスト氏の基調講演からはメッシュフリー、境界要素法など新技術により新しい領域へ踏み出していることが強く印象付けられました。
4.展示スペースにて
米国のみならずヨーロッパ、アジア圏からも多くのハード、ソフトベンダーが展示スペースに出展していました。展示会社の総数は30社に及びます。LS-DYNAとその関連商品がいかに幅広い関係をもっているかを如実に物語っているといえます。その中で日本総研ソリューションも展示ブースを構え、自社開発製品であるJSTAMPやHYSTAMP/HYCRASHの紹介を行いました(図4)。当社としては今後も日本国内だけでなく世界に向けた情報発信を積極的に行なっていきたいと考えています。






