
CAE Technical Library エンジニアレポート - CAE技術情報ライブラリ
2009.02.02
近年音に関するシミュレーションへの解析需要が高まっています。例えば自動車の分野であれば、電気自動車やハイブリッド車、高級自動車などではエンジン音など機械的な音が非常に小さくなり、これまであまり目立たなかった部分からの音が問題になっています。スポーツ用品なども音が設計上重要な項目であり、例えば高校野球で使用された金属バットの打撃音が問題になったりしました。航空機などの分野では、音と構造の連成が1つの課題です。さらに住宅メーカーなどでも、室内を歩く場合に発生する音の解析などが研究されています。 音は非常に身近な存在ですが、その発生源や伝播の様子を解析するのは非常に難しく、また騒音などの対策は、実験や経験による部分が多くを占めていました。しかし最近では音を解析するプログラムの精度向上や計算機の能力向上に伴い、いろいろな場面で音の解析が行われるようになってきています。 LS-DYNAは従来から流体と構造の連成が可能だったので、音の発生と空間の伝わり方の解析に対して適用されてきました。さらに現在開発中のバージョンでは、より進んだ音の解析手法として、境界要素法が使用可能となります。 今回は音の解析について、現在の機能と新しい機能の紹介をさせていただきます。
LS-DYNAによる音の解析方法
音の解析については、解析対象や問題のレベル、必要な結果などに応じていくつかの方法があります。一定の振動源がある場合は、音が伝わる空間(=空気の部分)もメッシュでモデル化して固有値解析を行うような手法があります。いろいろな音が混じっているような場合は、周波数応答解析のようにする方法も考えられます。LS-DYNAの流体-構造連成解析機能を使用した場合には、空間を伝わる音を時系列で解析することが可能です。 図1 にその概要を示します。
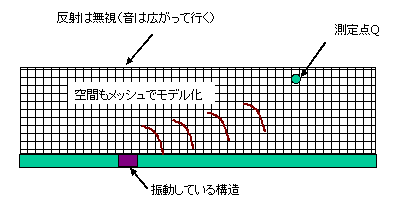 図1 LS-DYNAの流体-構造連成解析を使用した音の解析手法
図1 LS-DYNAの流体-構造連成解析を使用した音の解析手法
音の発生源と空間(空気)をメッシュでモデル化します。構造が振動して空気に振動を伝えるため、構造物と空気の間には拘束条件を定義します。このような手法による解析例を 図2 に示します。
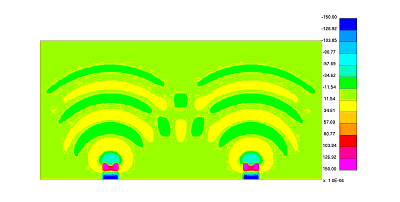 図2 流体-構造連成解析を使用した音の解析例
図2 流体-構造連成解析を使用した音の解析例
2つの音源から音が放射され、空間を伝わっていく様子を視覚的に確認することができます。このような連成解析では、1つの解析で構造の振動から音の伝わり方まで捉えることが可能ですが、測定点の音圧などの処理が難しいことと、実用的な計算ではモデル規模が大きくなって解析時間が非常にかかってしまう可能性があることなど課題がいくつかあります。
上記の各手法は構造解析をベースとした手法ですが、従来から音(音場)の解析には境界要素法も適用されてきました。境界要素法(BEM)の利点は 図3 に示すようにモデル化が非常に簡便であることです。
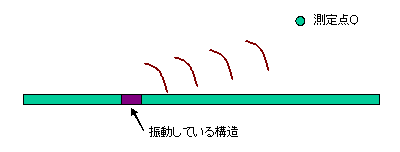 図3 境界要素法を使用した音の解析
図3 境界要素法を使用した音の解析
モデル化を行うのは基本的に振動している構造物のみとなります。
LS-DYNAにもこの境界要素法が実装されつつあり、次の新しいバージョンからご利用いただけます。
境界要素法を使用した音−構造連成解析
LS-DYNAの境界要素法解析を使用すれば、振動の発生から音場の解析まで1つの解析で実行可能です。 例えば、ゴルフクラブにボールが衝突して音が発生するなど、実用的な解析が現象をそのまま解析モデルに置き換えるだけで計算可能となります。従来であれば、衝撃解析や固有値を行い、周波数領域に直して解析するなどの手間がかかりました。LS-DYNAならばこれら一連の解析を自動的に1つの実行で解析できます。その概要を 図4 に示します。
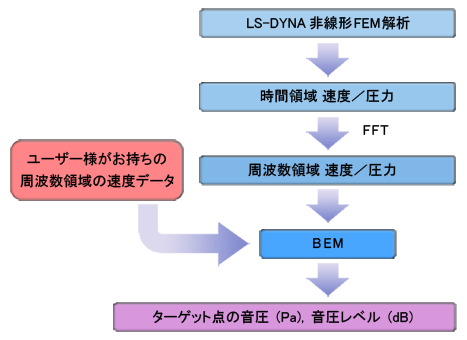 図4 LS-DYNAによるBEMを利用した音の解析手法
図4 LS-DYNAによるBEMを利用した音の解析手法
また、境界要素法では、大規模な行列を処理する必要がありますが、LS-DYNAのBEMソルバーはいくつかの手法を適用して、部分領域に分けたり、MPPで使えるように工夫したりして、実用的な時間で計算可能となるように開発を進めています。図5には検証解析の1例を示します。
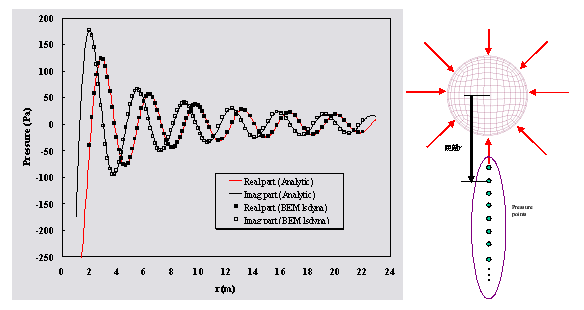 図5 LS-DYNAによるBEMを利用した音の解析例
図5 LS-DYNAによるBEMを利用した音の解析例
振動する球体の中心から一定距離にある測定点の音圧をプロットしました。解析結果と理論解(analytic)とはよく一致しています。
まとめ
LS-DYNAで開発中の新しい境界要素法解析機能についてご紹介しました。音の解析はこれからもますます重要となり、解析ニーズも増えていくと思われます。LS-DYNAの開発思想は1つのプログラムで必要な解析機能を標準で装備し、ユーザー様のより幅広いニーズや精度向上に役立てる、というものです。今回ご紹介した境界要素法もその思想に基づき開発されています。今後もユーザー様のニーズを満足させる機能を開発していく予定です。ご興味のあるユーザー様は是非弊社までお問い合わせいください。ユーザー様のご意見やご要望をLS-DYNAの開発にも反映させていきたいと思います。





