
CAE Technical Library エンジニアレポート - CAE技術情報ライブラリ
2012.04.02
あるFEMセミナーでの出来事
今から30年前のことです。企業向けのFEMセミナーで講師(戸川隼人 先生1))が、次のことを言われました。
- FEMをうまく使うコツは二つあります。
- (1) 難しいことは、やらない。
- (2) もし難しいことを行う場合は、徹底的に突っ込んで行う。ただし、そのため、その人の人生は悲惨に終わるかもしれないが、それはそれで日本のFEMの文化向上に尽くしたことになるから意義のあることである。
最近FEMに関するセミナーは花盛りですが手続きの説明が多く、ここまで端的にFEM道を教えてくれる先生には、なかなかお目にかかれません。私は講師の華麗な数学的説明は、すっかり忘れてしまったのですが、この二つのコツだけは30年間気になって「人生、悲惨にはなりたくない」と(1)と(2)のバランス取りに気を使ってきました。今改めてこのコツの意味を考え直すと、(1)は企業人向けに「実験を含めた現実的なCAEの重要性」を強調したものであり、(2)は企業内研究者 or CAEプロフェッショナルに対して「先端FEMについては、基礎的なことをしっかり踏まえて、それなりの覚悟を持って臨みなさい」という叱咤激励の意味と解釈します。
(1)と(2)に共通することは「CAEを進める過程では、いくつかの選択を迫られる」ということです。その一つである「数多い汎用FEMソフトの中から何を選ぶか?」については、前回2)ご説明しました。
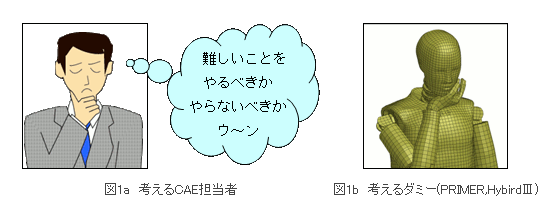
選択の科学
NHKで放映されたコロンビア大学白熱教室3)のシーナ・アイエンガー教授の講義「選択の科学4)」が話題になっています。ここで使われている「選択」は「choosingで、自己判断を伴う選択」です。この講義の人気の理由は、選択を適切に行うことによって人生が豊かになることを、具体的に分かりやすく説明していることのようです。この講義は数回のシリーズものですが、その中の一節が印象的でした。
- <選択が多くて迷う場合の対処方法>
- 選択の対象が多いと一般人は迷って適切な判断ができなくなる。それに対して、専門家は三つのことができる。
- (a) 選択を単純化する。
- (b) 選択を分類する。
- (c) 選択の優先順位をつける。
実は、これらは私たちが日常活動で知らず知らずのうちに行なっている行動です。CAEにおいても、(a)解析対象を理想化・単純化して、(b)解析の種類を分類検討して(構造解析か、熱解析か、連成解析か、あるいは材料力学を駆使して手計算でできないか等)、(c)解析フェーズを分けてスケジュールを立てる、言い換えると優先順位をつけます。
さて、ある企業のCAE推進部門では、ベテランCAE屋は対象となるテーマをよく精査してポイントを絞ったモデルを考案して、なんとか課題を解決します。無意識のうちに上記の(a),(b),(c)を実践しています。一方、ハードが進歩してソフトの操作性も向上した昨今、若い方々がチャレンジ精神を発揮していきなり大規模で複雑な解析に取り組む傾向がみられます。解析して何を評価するか曖昧なまま、まず解くことに関心が向います。そのいちずな精神は尊いのですが、高度非線形解析はトライすれば期待した結果が必ずしも得られるものではありません。ユーザ会で発表されるのはサクセスストーリーであって、失敗例は表立って語られません。ユーザ会でたまに講演者が語る苦労話は貴重です。
このコラムを読まれている皆さんはCAEの専門家ですかor初心者ですか? もし、専門家を自認されるのであれば、ぜひ上記の(a),(b),(c)を心がけて下さい。これは、私の意見ではありません。なにせアメリカの名門コロンビア大学の教授の教えです。コロンビア大学は、創立1754年、ノーベル賞受賞者97人を輩出、またオバマ大統領など歴代多くのアメリカ大統領が学んだ超名門大学です。そこの先生の教えですから、きっと本当に違いありません。
コンテンツ01 タイトル
歯車の研究は古くて新しいテーマで、現在でも様々な研究開発が続けられています。ご紹介する解析対象は自動車の操舵機構等に使われるウォームギヤ(図2)です。
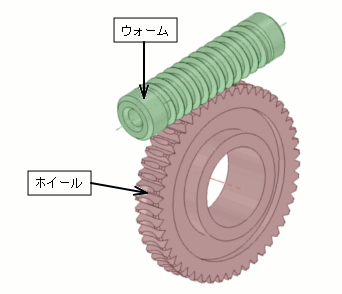 図2 ウォ−ムとホイール
図2 ウォ−ムとホイール
設計部門の狙いは「スムースなかみ合わせによる騒音の低減化」ですが、いきなりウォームギヤを含む駆動装置全体の音響解析のようなことはしないで、以下のような現実的な解析戦略を立てます。目標とする工数は数日内、できれば1 Day Solutionを目指します。以下の(a),(b)および(c)は、前述に対応しています。
- (a) 選択の単純化
- 解析モデルは、音源であるウォ−ムとホイールに限定します。
- (b) 選択の分類
- 解析方法についてはLS-DYNAの過渡解析とします。本来、歯車の機構解析については、ADAMSのような機構解析ツールに優位性がありますが、歯面形状を高精度にモデル化した弾性接触解析になるとADAMSでも計算時間が飛躍的に増加して、機構解析のメリットがなくなります。ならば今回、より汎用性のある陽解法FEMで行うことにします。
- (c) 選択の優先順位づけ
- まず、ウォ−ムとホイールを剛体として短時間で結果の得られる剛体接触解析を行います。ただし接触面間のペナルティー剛性を調整して、剛体解析でも弾性接触に近い接触状態(接触圧コンター)を評価できるように努めます。より厳密な弾性モデルによる精度向上については、次のフェーズとします。
以下に解析結果を示します。剛体モデルで、複雑なウォームギヤのかみ合わせ状態の見える化を実現できました。設計部署では別途、歯車理論による詳細な検討も行われます。今後の課題は歯面の厳密な詳細モデル化および弾性解析の実施です。
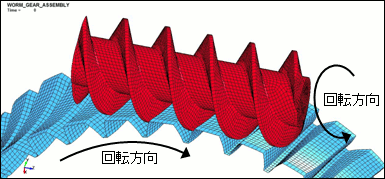 図3 メッシュモデル
図3 メッシュモデル
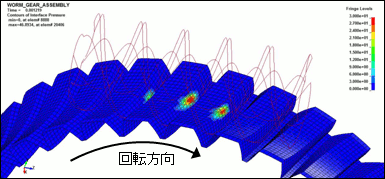 図4 接触圧力コンター(ホイール側だけを表示)
図4 接触圧力コンター(ホイール側だけを表示)
まとめ
ものづくりメーカでは、CAEは設計部署にタイムリーに対応することが望まれます。そこでは実現性に乏しい難しい解析に取り組むより、まずは、できることを速く行い結果を関係者に見せて議論することが優先されます。本コラムの最初の戸川先生のコメント(1)もその趣旨と考えます。その経験を積むと、次第に難しい解析にも見通しを持って対応できるようになります。そのためには、シーナ・アイエンガーの言葉を借りれば「(a)解析の単純化、(b)分類および(c)優先順位づけ」を行うことが必要ではないでしょうか? それを自然体でできるようになればベテランCAE屋です。
筆者の紹介
徳満 祥三
株式会社JSOL エンジニアリングビジネス事業部 技術顧問。カヤバ工業株式会社(現KYB株式会社)にて、CAEによる各種油圧機器の開発支援およびCAEの社内展開に従事。2011年3月定年退職、現在に至る。
- 参考資料
-
- (1) 戸川隼人 氏の略歴を紹介しているWEBサイト
http://www.amazon.co.jp/%E6%88%B8%E5%B7%9D-%E9%9A%BC%E4%BA%BA/e/B004L0JMJU - (2) JSOL News Letter Vol.37 FEMソフトの選定について
- (3) NHKコロンビア白熱教室、シーナ・アイエンガー教授の「選択の科学」を紹介しているWEBサイト
http://www.nhk.or.jp/hakunetsu/columbia/about.html - (4) 選択の科学、著者:シーナ・アイエンガー、翻訳:櫻井 祐子、出版社: 文藝春秋、発売日: 2010年11月
- (1) 戸川隼人 氏の略歴を紹介しているWEBサイト





