
CAE Technical Library �G���W�j�A���|�[�g - CAE�Z�p��C�u����
2012.03.01
FEM�\�t�g�̑I��ɂ��āi���͂� ��= F�^A �łȂ��� ��=�ςb�u �ɂȂ�ꍇ������j
- �J�e�S���[
- �F �\�����
- �֘A���i
- �F LS-DYNA
FEM�\�t�g�̑I��̖ڈ�
�̂����Ƃ�CAE���u���Ⴂ���X�̔Y�݂̈�Ɂu�����̏��p�ėpFEM�\�t�g�̒����玩���̋Ɩ��Ɉ�ԓK�����\�t�g�͉����낤�H�@�v���[��������Ăǂ��I�ׂ悢�̂�������Ȃ��v������܂��B����͏���������ł��B�Ȃ��Ȃ�u�ǂ̃\�t�g���悢���v�͉�͋@�\�����łȂ��u�g����n�[�h���A�l���܂ސE����A��͖ړI�A�\�Z����ђS���҂�CAE�̃o�b�N�O�����h���v�ɂ���T�ɂ͌����Ȃ�����ł��B
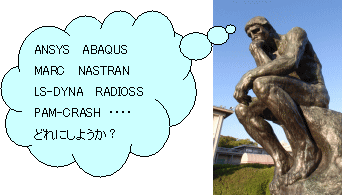 �}1a �l����l
�}1a �l����l
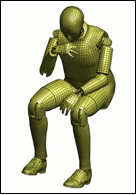 �}1b �l����_�~�[�iPRIMER,Hybrid�V�j
�}1b �l����_�~�[�iPRIMER,Hybrid�V�j
�����A������15�N���炢�O�܂ł́A�\���n�ėpFEM�\�t�g�͔ėp�Ƃ͌����Ă��J���̌o�܂ɂ�蓾�ӕ��삪����܂����B�������ŋ߂͂ǂ̃\�t�g���@�\���[�������A�܂����������\�t�g�����[�N�x���`�`���Ńp�b�P�[�W�̒��ɕ��ׂ��肵�Ĕėp�\�t�g�Ƃ��Ă̊����x�����߂���̂ŁA��͋@�\����������Ɛ̂̂悤�ȍ��ʐ������m�ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B���Ƃ���30�N�O�ɂ́u�Ɏ~�܂��Ă���w���R�v�^�[�̍\����͂�NASTRAN�ł����ł��Ȃ��v�Ƃ����܂������A����ɕK�v�ȁu���������[�t�̋@�\�v�́A����قƂ�ǂ̃\�t�g�ɔ�����Ă��܂��BLS-DYNA�����ӂƂ��Ă������I����`���ɂ��Ă����K�̓��f���ł���A�ǂ̃\�t�g�ł�������x�͉�����悤�ɂȂ�܂����B
���̌o���ł����ƁA��ƂŎg���\�t�g�ň�ԏd�v�Ȃ��Ƃ́u�v���傩��v������郌�x���̉�͂��ł��郍�o�X�g���v�Ǝv���܂��B����͕�����ɂ������Ƃł����A���Ƃ��u�z��@�R�[�h����K�͏Փˉ�͂���уG�A�o�b�O���܂ޗ��̍\���A���ɁANASTRAN����K�͌ŗL�l��͂ɁAABAQUS�̂悤�Ȕ���`�R�[�h���S����͂Ɏg���邱�Ɓv���������R�́A���f�����̃m�E�n�E���܂ޒ��N�̎��т����邩��ł��B�����ă\�t�g�����̐��ʂ𑁂��o���ɂ́A�������̋���g���[�j���O���̌�̃T�|�[�g�ɂ��Ƃ�����傫���̂ŁACAE�\�t�g�x���_�[�̑I����d�v�ł��B�\�t�g�I��ɍۂ��Ă͈ȏ�̂��Ƃ𑍍��I�ɔ��f���Đi�߂邱�Ƃ��]�܂�܂��B
�z��@�̕��y
�ŋ߂�FEM�̑傫�ȗ���̈�ɗz��@�̐v����ւ̓W�J���y������܂��B�z��@�̓����́A���͂���уG�l���M�[���̉ߓn�I�ȕω���ǂ����Ƃ��ł��邱�Ƃł��B��发�P�j������p�������Ő������܂��B
�}2�Ɏ�����[�Œ�̖_�̒[�ʂɃu���b�N��������A���̏u�Ԃɒ[�ʂɔ������鉞�͂��l���܂��B�����Ŗ_�ƃu���b�N�́A�F����̉�Ђ̐��i�ɒu�������Ă��������B��ʂɐv����ł́A�܂��������u�Ԃ̗�F��z�肵�ĐÓI�ȉ��̓Ё�F�^A���Z�o���āA�����]�����܂��B���i���n�m���Ă����Ƃ̐v�҂ł���u�������u�Ԃ̗͂�z��v�Ƃ����̂��o���I�ɑÓ��ɂł���̂ŁA���Ԃɒǂ���v������CAE�Ƃ��Ă͎��p�I�ł��B
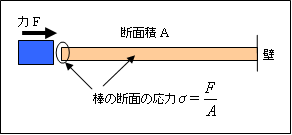 �}2 �ÓI�ȉ���
�}2 �ÓI�ȉ���
�i���͂͒f�ʂœ���A���ԕω����l���Ȃ��j
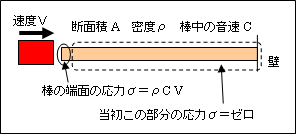 �}3 �Ռ�����
�}3 �Ռ�����
�i���͂͏Փ˂̏u�ԁA�[�ʂɔ����A���̌�A�_�̒���`�d���čs���j
����A���͔g�̓`�d���l���������͂͐}3�̂悤�ɂȂ�܂��B���̉��� �Ё���CV �́A�_�̖��x�ρA�_�̒���`��鉹��C����уu���b�N�̏Փˑ��xV�Ō��܂�A�_�̒���`�d���Ĕ��Α��̒[�Ŕ��˂��čs�����藈���肵�܂��B���̂悤�ȉ��͂̎�����ϓ��ډ�͂���̂��z��@�̓����ł��B�������A���̒��x�̃��f���ł���ΉA��@�ł���͉\�ł����A���i���x���̕��G�ȃA�Z���u���̏Փˉ�͂��A��@�ōs�����Ƃ͌����I�ł���܂���B�A��@�Ɨz��@�̌����Ȑ����͏Ȃ��܂����A��Ƃ̐v���ꃌ�x���ł������茾���܂��ƁA�}2�̂悤�ɐÓI�ȗ͂̂荇�����牞�͂����߂�̂��A��@�A�}3�̂悤�ɉ��͔g�̓`�d���l����̂��z��@�Ɖ��߂��Ă悢�ł��B�}3�̏Ռ����͂ɂ��Ắu �^���ʂ̕ω����͐� �v�̊W����Z�o�ł���̂ŊS�̂�����͐�发�P�j���Q�Ƃ��������B
�Ռ���͂̋�̗�Ƃ��āA�{�[�����o�b�g�őł��(�}4)��JSOL��WEB�T�C�g�Ō��J����Ă��܂��B���̓R���^�[�̃A�j���[�V����������ƁA���͔g���o�b�g��������ɓ`�d����̂ŐԂ��R���^�[�̈�i���͂̍��������j���s�����藈���肵�Ă���l�q������܂��B���̂悤�ȏꍇ�A�A��@�ł͂����Ύ����������ɂȂ�܂����A�z��@�ł͂��ꂪ�Ȃ��̂ŏՓˉ�͂��e�Ղɉ\�ɂȂ�܂��B�܂��z��@���o������Ɖ��͂���уG�l���M�[�ω����ɑ���l�@�͂��[�܂�A�A��@�̗��p�Z�p�����サ�܂��B
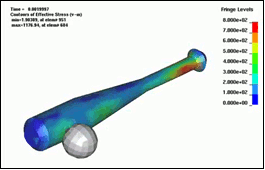 �}4 �{�[�����o�b�g�őł��
�}4 �{�[�����o�b�g�őł��
�iJSOL��WEB�T�C�g�Ō��J���j
�]���A�z��@�̎g�p�͎����ԃ��[�J��d�C�E�@�B�E�d�H�ƂȂLjꕔ�̑��ƂɌ����Ă��܂������A�n�[�h�̐i���ɂ�āA���[�U�w���L����K�p�͈͂��g�債����܂��B�M�҂̑O�E�i���i�@�탁�[�J�j�ł��A�\���n�ɂ��Ă͏]���̉A��@ANSYS�ɉ����Đ��N�O����LS-DYNA���g���n�߁AFEM�ɑ���m�����L�����邱�Ƃ��ł��܂����B���̓T�^�I�Ȏ���ɂ��Ă͑O���Q�j���Љ�܂����B����������z��@�\�t�g�̂Ȃ�����LS-DYNA��I�肵�����R�͈ȉ��ł��B����3��4�����ߎ�ł����B
- ����܂ŗz��@�ɖ��o���ŁA����̗z��@�\�t�g�ɌŎ����闝�R�͂Ȃ������B
- LS-DYNA�͐��E�ōł����y���Ă���z��@�\�t�g�ł���A�g�p���т��L�x�Ńx���_�[����K�ȗ��T���v�������ł���B
- ALE�@�ɂ�闬�̍\���A����͂��V���b�N�A�u�\�[�o�p�_���p�[�̃o���u��͂ɗL�p�������B
- �����g������p�I�ȃ^�C�����f���i�o�[�`�����f�W�^�C���j���������B
- ��Փx�̍�����͋@�\�ɂ�LSTC�͒���I�ɊJ����i�߂Ă���B���̈Ӗ��ŁALS-DYNA��Cutting�@Edge�@Code�i��[FEM�R�[�h�j�Ƃ����Ă���B
�܂Ƃ�
���ꂩ���CAE�ł́u�z��@�̐ϋɓI�Ȋ��p�v����Ɂu�z��@�ƉA��@�Ƃ̘A�g��́v���L�[�ɂȂ�Ǝv���܂��B�������݂̐E��ɗz��@�\�t�g�������Ă��Ȃ���A���Зz��@�\�t�g�̓��������������߂������܂��B�x���_�[�ɂ��Ă̓T�|�[�g���[�����Ă���x���_�[�������߂��܂��B���R�́A�T�|�[�g��p������������̂̐��Ƃ̗D�ꂽ�T�|�[�g���邱�Ƃɂ��A�����i���̂悢��͌��ʂ������邩��ł��BLS-DYNA�N���X�̖{�i�I�Ȕ���`�z��@�\�t�g�ɂȂ�ƍ��͈͂ȋ@�\��Ɗw�ŗ�������͍̂���ł��B�T�|�[�g���邱�Ƃɂ������Ԃ�{���Ɩ��ł��鐻�i�J���ɐU������邱�Ƃ��ł��܂��B
�X�|�[�c�ł��H�w�ł���B�̑����́u�D�G�ȃR�[�`�A�C���X�g���N�^�[��T�ɂ������Ɓv�ł��B�{�Ԃ̑O�Ɋ�{�g���[�j���O���s�����Ƃ��厖�ŁA�����s���ł����Ȃ荂�x�ȋZ�����݂�Ƃӂ������]�|���邱�Ƃ�����܂��B��Ƃł�CAE�𒅎��ɐi�߂�ɂ͊W�҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������܂߂���͐헪���d�v�ł��B
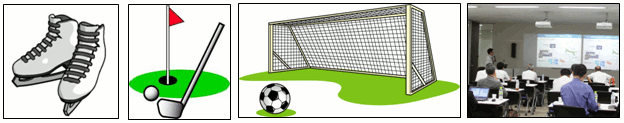 �}5 �������悢�R�[�`or�C���X�g���N�^�[������Ə�B������
�}5 �������悢�R�[�`or�C���X�g���N�^�[������Ə�B������
���́A���̂Â��胁�[�J�ŗl�X�ȔėpFEM�\�t�g�ɐG��Ă��܂����B�ǂ���悢�\�t�g�ł��̑��l���d�������Ǝv���܂��B�F�����낢��ȉ�̓e�[�}�Ƀ`�������W����āA���̂Â���̌���Ŋ���邱�Ƃ����҂������܂��B
�����āA���܂ɂ͋C���]����CAE�Ŏ��w���R�v�^�[�����܂��B���ĊF�l�̓c�[���Ƃ��ĉ����g����ł��傤���H
�}6 LS-DYNA�ɂ�鎆�w���R�v�^�[����Q�j
�M�҂̏Љ�
���� �ˎO
�������JSOL�@�G���W�j�A�����O�r�W�l�X���ƕ� �Z�p�ږ�B�J���o�H�Ɗ�����Ёi��KYB������Ёj�ɂāACAE�ɂ��e������@��̊J���x�������CAE�̎Г��W�J�ɏ]���B2011�N3����N�ސE�A���݂Ɏ���B
- �Q�l����
-
- (1) �ΐ�, ���, ���|, �ʕ{�F��b����̏Ռ��H�w, �X�k�o��, ��129�`130, 2009�N
- (2) �Z�p�ږ�A�C�̂������|LS-DYNA�Ŏ��w���R�v�^�[�������|





