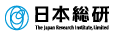-
![[写真1] W.M.Wilson 等による「たわみ角法」の発表論文の表題に用いられている不静定構造(statically indeterminate structures)](/library/tachibana/img/vol28_p01.jpg) 画像拡大
画像拡大
[写真1] W.M.Wilson 等による「たわみ角法」の発表論文の表題に用いられている不静定構造(statically indeterminate structures)
10 CONTINUE
重要なポイントは、不静定構造ではマジメに頑張るほど、つまり剛性が周りよりも大きいほど大きな力を負担する、ということだ。
ちなみに不静定構造は statically indeterminate structures からの訳語であり、写真-1でもわかるようにWilson 等は「たわみ角法」の表題にも使っている[1]。
おっと、ちょっと待った。大学では、「力の釣り合い条件」だけで部材の断面力が求まるのが静定構造で、不静定構造だと、それ以外に「部材の力と変形の関係」や「変形の適合条件」も必要となる、と習ったような気がするが・・・、それは?
確かにそうだ。しかしそれだけでは試験で点をとれても設計者としてはどうだろうか?
例えば、中(なか)廊下型3スパンのホテルの設計を考えよう。スパン方向の梁の長さの比を 3 : 1 : 3 とし、断面は同じとしよう。「梁の曲げ剛性は長さに逆比例する」ので中廊下の梁の剛性は両どなりの梁の剛性の3倍となる。従ってもし地震水平力が加わると、中廊下の梁に大きな曲げモーメントが生じることになる(実際に計算例で示すのは省略)。ひょっとしたら、その梁が降伏してしまうかもしれない。心配症の優等生なら安全のために中廊下の梁だけ鉄筋を増やして再計算するに違いない。しかし増やした分だけ剛性も大きくなり、益々そこにかかる曲げモーメントも大きくなる。さらに鉄筋を増やす。さらに・・・といった悪循環に陥る。
この悪循環の一つの解決法は、鉄筋を増やしたりするのではなく中廊下の梁の断面を少し細くして剛性を両側の梁の剛性に近づけることだ。これで曲げモーメントの分布も全体的にバランスがとれるようになる。
(あまりコロコロと断面を変えると施工費が高くなる、という問題も生じるが)
言い換えるなら、同一の節点に集まる構造要素の剛性は、なるべく近い値に調整しておく、といったところか。
なぜなら、この稿の標題のように不静定構造ではがんばる者に重荷がかかるからだ。
しかし、これで悟りを開いたなどと思わないでいただきたい。ゴルフを始めてから何度も悟りを開いたつもりになったが、一向に上手にならないのと同じだ。
場合によっては、応力が集中する部分を意図的に設計しておき、過大な荷重がかかったとき、その部分が真っ先に壊れ、全体に致命的な破壊が進展しないようにする設計方法もある。構造ヒューズもしくは応力制限機構(force limiting device)の考え方だ。その場合、建物の倒壊さえ避けられるなら、内装材などの2次部材の多少の被害を許容することになる。
不静定構造では、1箇所が壊れても応力の再配分がなされ持ちこたえる場合もあるが、1箇所でも壊れると全体崩壊にいたる「静定構造」がある。この構造は、「マジメ」であろうがなかろうが手抜きは一切できない。最初に述べた「酒屋のけーちんぼー塩まいておくれー」と叫ぶだけで、オミコシにぶらさがるようなことはできない。
この静定構造については次稿にゆずることにする。
ちょっと気になるのは、この歳になっても未だにオミコシにぶらさがっているだけなのかなー。
- [1] W.M.Wilson, F.E.Richart and Camillo Weiss, "Analysis of Statically indeterminate Structures by the Slope Deflection Method", Univ. of Illinois Engineering Experimental Station, Bulletin No.108, (1918), pp.1-214